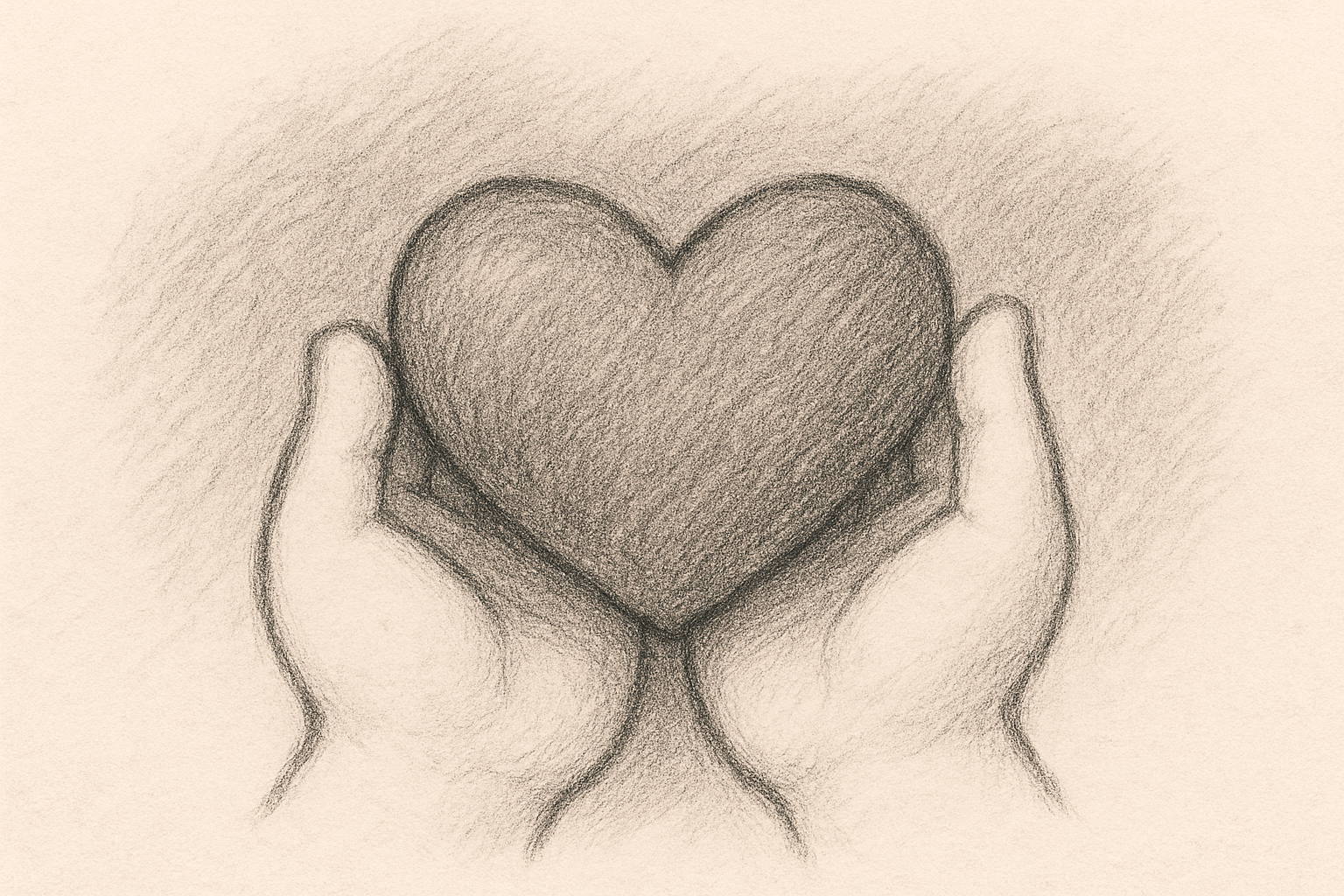「せんせい」にとって
みんながみんな こうすれば うまくいくっていう方法はない
「せんせい」もひと 子どももひと
だから そのとき そのひと同士のなかで
よい形を みつけていくことが たいせつ
必ずうまくいかない方法
反対に 必ずうまくいかないっていう方法はある
1 こころを傷つける
2 重箱の隅をつつく
3 ズレた話をし続ける
この3つの方法であれば、確実に子どもの学びや成長を妨げることができる
だから、うまくいく方法はないけど、必ずうまくいかない方法をさけることはできるって思う
1 こころを傷つける
これはそのまま
コドモノこころを傷つけたら もう なにもうまくいかない
いくら 言葉で飾っても いくら 理屈をこねても
でも けっこう そんな態度や言葉が
学校のなかにある
これをやれば かんたんに 子どもの学びがうまくいかなくなる
だから その反対をするといい
注意深く この方法を 避けるといい
うまくいく方法はないけど すてきな学びにつながる可能性が生まれる
2 重箱の隅をつつく
これは おもしろい
「せんせい」じゃなくて 先生になっちゃうと 細かいところに目が行きやすい
あるいは 細かいところが気になっちゃう
何十年 先生を続ければ 続けるほど
その傾向は強くなる
それを 大事にすることが 子どものみらいにつながるって
本気で そう思えてきちゃう
でも たぶん ほとんど 意味がない
そんなふうに 思っている先生の常識は
子どもたちが大人になるころには
忘れさられた常識 すでに非常識になっている
重箱の隅が大事だと思えちゃう
重箱の隅は ほとんどの人は気にしない
だから それを気にしている自分が 有能な気分になっちゃう
そう そして そのうち それが目的になっちゃう
すでに そこには 子どもはいない
これをやれば かんたんに 子どもの学びがうまくいかなくなる
だから その反対をするといい
注意深く この方法を 避けるといい
うまくいく方法はないけど すてきな学びにつながる可能性が生まれる
3 ズレた話をし続ける
これは絶妙
先生は「本当」に本気
だから難しい でも その「本当」の先に
「本当」の「ほんとう」がある
先生は自分の「本当」だけを見つめちゃいやすい
そのままいくと 言っていること 言っている内容は 日々ズレていく
微妙に ズレたことを言い続けるってこと
子どもが「?」ってなることを言い続けるってこと
そんな状況にある先生は
目のまえの子どもたちが
自分よりも「至らない存在」なんだと思っている
「ほんとう」は 学級のなかに 自分よりはるかに魅力のある
自分よりも おもしろい 自分よりも ある能力に関してはるかに長けている
そんな子どもがたくさんいる
そんな事実に気づいていない
自分の方が子どもたちよりも長けている
そんな気持ちがちょっとでもあると
先生の話は ちょっとずつズレていく
そして そのうちちょっとずつそのズレは大きくなって
全部が よく分からなくなる
この先生は 何を言ってるの?って 子どもたちは 日々真剣に「?」と向き合うようになり そのうち 「ほんとう」に嫌になる
だから その反対をするといい
注意深く この方法を 避けるといい
うまくいく方法はないけど すてきな学びにつながる可能性が生まれる
インスタント教育ってない
子どもたちとの日々に インスタント的な方法はないと思う
みんな それは わかっているでしょ
だから 方法論とか 法則とかって
そんな言葉を聞くと すごく残念になる
注意深く さけること 方法論だとか 法則とか
注意深く さけること うまくいかない方法を
注意深く さけること 子どもの上に立つ先生になることを
それが 「せんせい」の第一歩かも
あるいは 毎日 考え続けなくちゃいけないことなのかも
「せんせい」であるために
いま ぼくは そんなふうに思ってる